~子育て中の親の皆さんへ~「子どもの成績が良くない」「親の言うことを聞かない」これは「子育て」が上手くいかなかったからではありません。そもそも親の「子育て」は子どもに影響はないのです。子どもを形成は「遺伝」と「環境」によって決まるからです。今回は「遺伝行動学」の視点から、「子育て」の勘違いについてお話します。

いい高校に進学して、いい大学に行ってほしいけど、成績がイマイチなのよねえ。私の教育方針が間違っていたのかしら?
この頃、言うことをくれないなあ。子育ての仕方が悪かったのかしら?

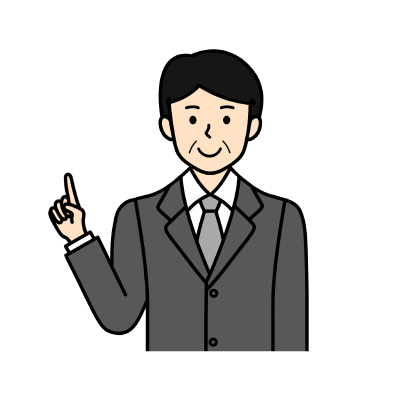
このように悩むお母さんは多いことでしょう。ですが、これは「子育て」の失敗に原因があるわけではありません。
なぜなら、子どもの成長は「子育て」とは関係なく、「遺伝」と「環境」で決まるからです。
行動遺伝学は、親に対して、残酷な結果を示しています。子どもの人間形成に、親の「しつけ」は影響しないというのです。
本当にそんな事実があるのでしょうか?
子どもの形成は「遺伝」と「環境」で決まる?
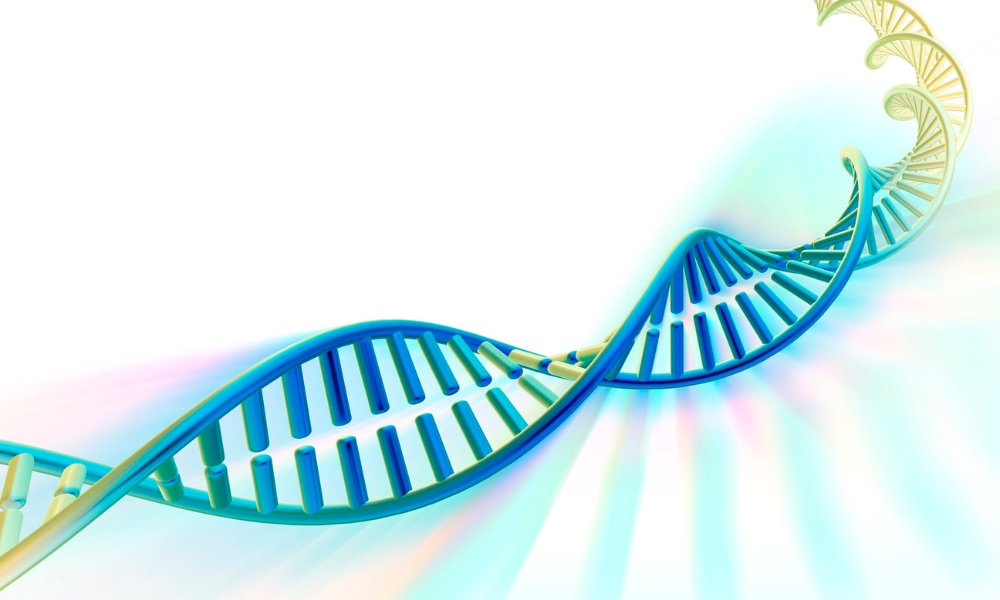
「社交性のある子どもに育てたい」「いい学校に入れたい」「素直で優しい子に育てたい」という「期待」を持ちながら、「しつけ」をしたり「子育て」するのは、親として当然のことです。
ですが、「子どもの人間形成」に、「しつけ」や「子育て」はほとんど無関係なのです。
行動遺伝学によれば、人間の形成は、「遺伝∔環境」で決まるというのです。
「環境」が影響するというのなら、親との環境(しつけ)が影響するのでは?
と思われるでしょうが、ここで言う「環境」とは「非共有環境」を指しています。
「非共有環境」とは何か?
環境には、「共有環境」と「非共有環境」があります。
「共有環境」とは、親と子どもが共有している環境、すなわち「家庭環境」です。
「非共有環境」とは、親と子どもが共有していない環境、すなわち、子どもなら「学校」や「友達関係」、親なら「会社」「同僚や上司のと関係」ということです。
そして、子どもに影響を与える「環境」とは、「非共有環境」を指しています。
つまり、子どもの成長に関わるのは、「遺伝」+「非共有環境」であり、親とかかわりが深い「共有環境」はほどんど影響しないというのです。
ここからは、遺伝と非共有環境が子どもに与える影響について詳しく見ていきます。
「こころ」も遺伝するのか?
身体的な特徴、例えば顔つきや、身長、体格などが遺伝する、ということはほどんどの人が納得できるでしょう。
では「こころ」も遺伝するのでしょうか?
答えはYESです。
行動遺伝学では、「知能」「性格」「精神的疾患」など、「こころ」に関することも、遺伝が大きく影響していることが分かっています。
では、親が影響を与えることないのか?
影響する部分はあります。
それは、「言語」「生活習慣」についてです。
日本人の親に生まれて、日本語を聞いていれば、子どもは日本語を話すし、話し方のクセなども、親の影響を受けます。
また、毎朝・晩歯を磨くなどの「生活習慣」も親の影響を受けます。
「言語」や「生活習慣」と同様に、
「内向的な性格を外向的な性格にする」
「算数を好きにさせる」ことができるのでは? と思う親は多いでしょう。
ですが、行動遺伝学によれば、このような「知性」「性格」に関わることについては、「共有環境」すなわち、親の影響はほとんど見られない、というのです。
では次に、「遺伝」と「環境」が、子どもの能力や性格などに、どのくらい影響するのか、ということについて見てみましょう。
遺伝と環境が影響することとは?
「遺伝率」(親の遺伝子がどのくらいの割合で子どもに遺伝するか)「非共有環境」「共有環境」の3つが、子どものどんな能力に影響するのかをまとめた表です
| 遺伝率 | 非共有環境 | 共有環境 | ||
|---|---|---|---|---|
| 認知能力 | 学業成績 論理的推論能力 言語性知能 空間性知能 一般知能 | 55 68 14 70 77 | 29 31 28 29 23 | 17 – 58 – – |
| 性格 | 神経症傾向 外向性 開放性 調和性 誠実性 興味・関心 損害回避 報酬依存 固執 自己志向 協調 | 46 46 52 36 52 34 41 44 37 49 47 | 54 54 48 64 48 66 59 56 63 51 53 | – – – – – – – – – – – |
| 才能 | 音楽 美術 文才 外国語 数学 スポーツ 記憶 知識 | 92 56 83 50 87 85 56 62 | 20 8 44 17 27 15 44 38 | – – – 23 – – – – |
この表を見ると分かるように、「性格」については、「遺伝」と「非共有環境」が大体50:50。
「音楽」「文才」「数学」「スポーツ」については、圧倒的に「遺伝」の影響が強く出ます。
ですが、「共有環境」が影響する項目は、「言語的能力」「学業」「外国語」のみとなっています。
つまり、「共有環境」=「家庭環境」は、子どもの人間形成にあまり影響しないことが分かります。
では、次に、なぜこれほどまでに「非共有環境」の影響が大きいのか見ていきましょう。
双子は同じ人生を歩むか?

行動遺伝学では、一卵性双子の研究が多くなされています。
一卵性双生児は、卵子が同じなので、全く同じ遺伝子を持っています。
この双生児の研究によれば、「性格」の遺伝率は、35~50%。
残りの50%ほどは、「環境」の影響によるものです。
昔のことわざ「氏(遺伝)が半分、育ち(環境)が半分」を裏付けるような結果と言えます。
一卵性双生児は同じ遺伝子を持ち、同じ家庭環境で育つので、かなり似てくることは、当然と言えます。
ですが、研究が進むにつれて、大きな疑問に突き当ることになります。
生まれてすぐに、文化や育て方が違う外国に養子に出された一卵性双生児の子どもが、まるで、同じ家庭環境で育ったかのように、2人とも似たような人生を歩んでいる事例が多く見られたのです。
遺伝率が50%ということは、残りの50%は環境で決まります。
2人は違う環境で生活しているので、違う人生を歩むはずです。
「家庭環境」は子どもの成長に関係ない、「非共有環境」が影響するのだとしても、生活環境が違えば「非共有環境」も全く違うはずです。
「非共有環境」が違えば、違う人生を送る可能性が高いわけですが、似たような人生を送る双子は多いというのです。
これはどうしてなのでしょうか?
この謎に答えることで、なぜ「非共有環境」が子どもの成長に大きな影響を与えるのかが分かります。
2組の双子が送った2つの人生から、その答えに迫ってみましょう。
2組の双子が送った驚きの人生
ここでは、まずある2組の一卵性双生児が辿った、驚きの人生を紹介します。
ケース1
生まれてすぐに里親に出された、一卵性双生児が39年ぶりに再会しました。アメリまでの出来事です。
全く違う環境で育ったにもかかわらず、2人には以下のように、様々な類似点があったのです。
- 2人とも、やや高血圧気味で、ひどい片頭痛に悩まされていた
- 1人は高校時代に落第し、もう1人も落第ギリギリの成績を取っていた
- 2人とも同じ車に乗り、タバコの銘柄も同じ
- 2人とも改造カーレースが好きで、野球嫌い
- 2人とも2度の離婚歴があるしかも、
- 最初の妻の名前が、どちらも「リンダ」で、2度目の妻は、どちらも「ベティ」
- 長男の名前は、どちらも「アラン」で、犬の名前も同じ「トイ」と名付けている
ここまで、同じだと、「あやしいのでは」と思う方もいるでしょうが、同じように、一卵性双生児が似たような人生を送っている例が、いくつも報告されているのです。
ケース2
次は、全く逆の人生を送っている一卵性双生児の姉妹の例。
それぞれ、別々に里親に出された一卵性双生児の姉妹。この2人が成年になったとき、1人はプロのピアニストになり、もう1人は音符すら読めませんでした。
養母の1人は、家でピアノ教室を開いている音楽教師で、もう一方の養母は、音楽とは全く縁がありませんでした。
ここまでは、当たり前のお話。
ですが、奇妙なのはここからなのです。
娘をプロのピアニストに育てたのは、実は音楽に全く縁がなかった方の親で、音符すら読めない娘の親は、ピアノ教師の方だったのです。
先ほどの遺伝率の表が示す通り、「音楽性」は遺伝による影響が極めて高い分野です。
一卵性双生児の姉妹はどちらも、どちらも高い音楽の才能を受け継いでいたはずです。
「家庭環境」や「子育て」が子どもの将来を決めるのであるなら、
ピアノ教師に育てられた娘が、プロのピアニストになるはずだし、音楽に縁のない親に育てられた娘は、音楽とは縁のない生活をするはずです。
それなのに、結果は「真逆」になっているのです。
以上、2組の一卵性双生児が送った奇妙な人生を紹介しました。
ではなぜ、このように奇妙な2つのケースが発生するのでしょうか?
それに答えたのが、アメリカの心理学者、ジュディス・リッチ・ハリスでした。
子どもにとって、「社会」とは「友だち関係」?
ハリス氏は、「子どもの人格は、遺伝と友だち関係との相互作用によって形成される」と考えました。
子どもは、「友だちグループ」の中で、目立つように、もしくは生き残れるように、自分の「立ち位置」を見つけます。
どんな「友だちグループ」にも、内(俺たち)と外(奴ら)があります。
女の子なら、ファッション、男の子ならゲームやスポーツ(あるいは、非行行動)について、暗黙のルールがあります。
子どもたちは、この「暗黙のルール」の中で、自分のキャラクター(役割)を決めて、自分の「居場所」を確保します。
このように、子どもの人格は、遺伝的要素を土台として、友だち関係の中で形成されていくのです。
こうして考えると、今回の記事の題にもある「なぜ子どもは親の言うことを聞かないのか?」という疑問に対しても、答えることができます。
勉強や遊び、ファッションでも、「子どもグループ」のルールと、家庭の「しつけ」が衝突した場合、子どもが親の言うことを聞くことは、絶対にありません。
皆さんも子どもの頃に、経験があるでしょう。
親より、友だち関係の方を優先したはずです。
そうしなければ、グループから排除され、「社会的」に死んでしまうからです。
こうしたハリス氏の主張から、先の紹介した一卵性双生児の奇妙な人生にも、答えることができます。
2組の双子はなぜ真逆の人生を歩んだのか?
まずは1つ目のパターンについて。
子どもは、自分に似た子どもに引き寄せられます。
一卵性双生児は、同一の遺伝子を持っているので、別々の家庭環境で育っていても、同じような友だち関係を作り、そのグループの中で、同じような役割を選択する可能性が高い。
遺伝と友だち関係(非共有環境)が同じなら、同じような人格が形成される可能性は大きくなり、
別々の環境に育ったにも関わらず、似たような人生を歩むことになるのです。
次に2つ目のパターンについて。
音楽と無縁の環境で育っていても、何かのきっかけ(例えば、学習発表会でピアノの弾くなど)で、音楽の才能があることに気づく。
彼女が、子どもグループの中で、自分を目立たせようとすれば、その利点を最大限に生かそうとするでしょう。
音楽によって、友だちから注目され、それが「報酬」となって、益々音楽を好きになっていくでしょう。
それに対して、音楽教師の娘の場合、周りが音楽関係の子どもたちばかりだから、少しくらいピアノが上手でも、目立たないし、誰も褒めてはくれない。
ですから、音楽以外のこと、例えばメイクやファッションの方が目立てるなら、音楽に興味を持つ必要性はないのです。
以上のように、子どもは友だちとの関係の中で、自分の性格(キャラクター)を形成していきます。
どんな集団でも、リーダーや道化役がいます。
ですが、同じグループに2人のリーダー(道化)が共存することはありません。
キャラクターがかぶれば、どちらかが譲るしかグループ内で生きる術はありません。
このようにして、そのグループに所属できるキャラクターが違えば、同じ遺伝子を持っていたとしても、違う人生を歩むことになるのです。
以上、この2つのケースから、子どもの人格形成は、遺伝と友だち関係(非共有環境)によるところが大きいことが分かったと思います。
では、親は子どもにしてあげられることは無いのでしょうか? 親は無力なのでしょうか?
親ができることはあるのか?

ここまで、読んでくださったお父さん、お母さんの中でも、
「子育てはいつか報われるはずだ」という「子育て神話」を信じている方は多いでしょう。
ですが、ハリス氏は「それは、勘違いでしかないのだ」と結論づけています。
では、親は子どもの成長を、指をくわえて見ているしかないのでしょうか?
決して、そうではありません。
ここからは、
- 転校により人生が劇的に変わった黒人の少年
- 英才教育を受けた少年の人生
この2つの事例から、親が子どもにしてあげられることについてお話します。
1人の黒人少年の劇的変化
ハリス氏によれば、子どもの人生に大きな影響を与えるのは、「家庭環境」より「友だち関係」、それはつまり、子どもにとっては「学校環境」です。
日本の学校環境では、あまり馴染みはないでしょうが、アメリカでは、人種の違いによって、生徒たちの行動や成績に大きな差が生まれます。
人は、自分に似た人に引き寄せられるために、人種別のグループを作ります。
そして、無意識のうちに、グループを人格化し、敵対するグループとは、全く違った「キャラクター」を持たせるのです。
白人グループと、黒人グループともなれば、それは顕著に現れます。
黒人のグループには厳然としたルールがある。
- 白人の子どもと付き合ってはならない
- 白人の子どもがするようなことをしてはいけない
大きくこの2つです。
白人の子どもが価値を置くことすべてを、黒人の子どもグループは否定します。
そして、その象徴となるのが「勉強して良い成績を取ること」なのです。
白人の子どもは「黒人は勉強のことをどうでもよいと思っている」と見るし、
黒人は、白人の子どもを「ガリ勉野郎で、俺たちとは違う」と見ています。
このようなグループの差が、知的能力の高い黒人の子どもを縛り付けるのです。
このことを劇的に示したのが、治安の悪いサウスブロンクスに住む1人の黒人少年のケースです。
この黒人少年をA君としましょう。
A君は、バスケットチームに入りたかったが、成績不振を理由に入部を許されず、その後高校を中退。
友人のうち3人は、麻薬がらみの事件に巻き込まれて死亡。
こうなると典型的な転落人生になるところを、A君は運よく、スラム街の子どもを遠く離れた土地に転居させるプログラムに選ばれました。
A君が転校したのは、ニューメキシコ州の田舎町。そして、白人の中流階級の子どもが通う学校に転校しました。
この学校で、A君の人生は劇的に変わることになります。
2年後、A君は高校のバスケットチームのエースになり、成績はAとBばかり。
ついには大学進学を目指すまでになります。
A君は、転校した学校で、自分の能力を発揮し、自分の居場所を確保したのです。
その後、古巣のスラム街を訪れたA君を見た、かつての友人たちは、A君の服装や話し方をおかしいと笑いました。
なぜなら、A君は、ブレザーの前ボタンをキチンと留め、中西部なまりでしゃべったからです。
新しい友だちグループの中で生き延びるには、中流階級の白人の子どもと同じような振る舞いをする必要があったのです。
子どもが、友だちグループの中で自己形成していくのなら、このように環境が変化することで、A君のように行動や性格が変化することになります。
英才教育は必要か?
19世紀末ごろは、どんな子どもでも、正しい訓練によって、天才に育てることができると信じられていました。
ここに出てくる少年をB君としましょう。
B君の両親も、それを信じて子どもの英才教育に人生をかけることにしました。
B君は、その英才教育のおかげで、すさまじい能力を発揮するようになります。
- 生後18か月で文章を読むようになり
- 6歳で数か国語の言語を操り
- 小学校に上がると、6カ月で公立学校の7年次まで修了
- 11歳でハーバード大学に入学
- 16歳でハーバードの学士号を取得
ですが、その後B君には転落人生が待っていました。
大学院に1年間在籍した後、ロースクールに進むも、結局学位は取れず、
大人になると、両親を避けるようになり、父親の葬儀にも現れることはありませんでした。
学問の世界からも離れ、頭を使わない安月給の事務仕事を転々として、46歳に心臓発作で他界。
その時は、独身で、無一文、完全な社会不適合者になっていたそうです。
ハリス氏は、このケースについて、以下のように述べています。
「B君のおかれた状況は、母親には育てられたが、仲間との付き合いがないまま成長したサルの状況と似ている」
仲間と関わらず成長したサルは、明らかな異常行動を示すと言われています。
同様に、英才教育受け、すさまじい能力を発揮したB君でしたが、幼少期に友だち関係から切り離されたことで、うまく自己を形成することができず、社会に適応することが出来なかった、というのです。
親が出来ることとは?
黒人少年の例では、少年の人生を劇的に変えたのは、「学校環境」であり、親の子育てとは関係ありませんでした。
そして、英才教育の例では、両親が子どものためを思い、受けさせた英才教育が、結果的にはその子を転落させることになりました。
では、親が子どもにして無力なのでしょうか?
この疑問に対するハルス氏の答えはシンプルです。
「親が無力であるというのは間違いである。なぜなら、親が子どもに与える環境(友だち・学校)が子どもの人生に大きな影響を与えるのだから。」
今の時代、こんなことを言うと「女性蔑視」だと批判されるでしょうが、
男女共学の学校に通う女子生徒は「数学や物理ができる女は可愛くない」と思われてきました。
(今の時代はどうかわかりませんが、私たちが学生の頃はそんな風潮が確かにありました。)
それが女子学生に対して、無言の圧力になるのです。
「バカで可愛い女」でなければ、友だちグループに居られないなら、たとえ数学や物理が好きであっても、勉強をやめてしまいます。
このように考えれば、親の一番の役割とは、
「子どもの才能を摘むことのない環境を与えることである。」
とハリス氏は言います。
知的能力を伸ばそうとするなら、良い成績を取ることが「イジメ」などの原因にならない学校に通わせるべきです。
女性の政治家や科学者が、女子高出身が多いのは、男女共学と違い「バカで可愛い女」を演じる必要がないからです。
同様に、芸術的才能を伸ばしたいのなら、風変りでも、バカにされたり、仲間外れにされない環境が必要でしょう。
子どもが、何ものにも「束縛」されず、その能力を伸ばせる環境を与えることこそが、親がしてあげられることなのです。
おわりに代えて
以上、子どもの成長は、「遺伝」と「環境」で決定づけられる。
その環境とは、非共有環境(=友だち・学校)であり、親はそれに介入することはできない。
ということをお話してきました。
ただ親は全くの無力ではなく、子どもにとって良い環境を与えることが、親にできることであり、その環境が子どもの成長に大きな影響を与えることがお分かり頂けたと思います。
ただし、どんな環境を与えたとしても、その環境の中で、何を選択し、どう振る舞うかを決定するのは子ども自身です。
子どもの将来を心配し、幸せな人生を歩んで欲しいと願うのは、親として当たり前のことと思います。
ですが、どのような人生を選ぶのかは、子どもであり、親ではない、ということを忘れてはいけません。
だから、子どもは親の思った通りには育ってくれないのです。
あなたは、あなたの親が思った通りの人生を歩んでいますか?
おしまい
※今回の記事は、橘 玲氏の著書「言ってはいけない~残酷すぎる事実~」を大幅に再構成させて頂いたものです。



コメント